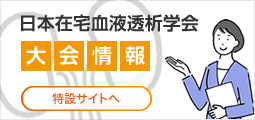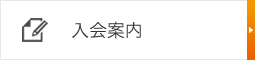在宅血液透析学会は社会的ならびに医療経済的環境の整備を行うとともに、在宅透析治療の普及・発展をはかり、医療の向上に寄与すること目的としています。
- トップ
- 在宅血液透析について
- よくある質問
在宅血液透析FAQ
患者さんに関すること
Q1. 在宅血液透析の訓練期間はどれぐらいですか?
A.施設により異なりますが、1~6か月の訓練期間を設けているところが多いようです。また、知識・技術の習得の速さには個人差がありますので、個々の患者さんによって訓練期間は変わってきます。
Q2. 訓練期間は何をおぼえるのですか?
A. 安全な在宅血液透析を行うために、自己管理につながる知識項目と、治療に必要な技術項目をおぼえます。知識は、腎不全および血液透析などの疾患や治療内容に関するものと、バスキュラーアクセスや食事の管理、検査データの理解など日常生活管理に関するものを習得する必要があります。技術については治療の準備、自己穿刺を含む開始・終了操作、透析中の異常・事故の対処方法などを習得します。
Q3. 自宅で体調不良(風邪、腹痛など)で困った時、どうしたらいいのですか?
A.主治医に連絡して下さい。管理施設が遠方で受診困難な場合は、自宅近くの医療施設を受診するよう指示される場合もあります。
Q4. 透析中の血圧低下にはどう対応しますか?
A.在宅血液透析で透析時間、透析回数を増やすことにより、透析時の総除水量や時間あたりの除水量を減らすことができます。除水量が減れば血圧低下は起こりにくくなります。しかし、通常とは異なる血圧低下など異常が生じた場合は、速やかに透析を中止し管理施設に連絡してください。患者本人による連絡が困難な場合は、介助者が連絡してください。
Q5. 旅行などの際は、どうしたらいいですか?
A.旅行などで在宅血液透析が行えない時は、施設での臨時血液透析が必要になります。
Q6. 食事・飲水制限はありますか?
A.透析時間、透析回数を増やすことにより透析量が増えれば、食事と飲水は健常人と同じくらいでも問題なくなります。ただし、健常人でも暴飲暴食をしても良いわけではありませんし、糖尿病などの疾患による食事制限はあります。また当然ですが、透析量が少ない場合は食事・飲水制限が必要です。
Q7. 除水量を自分で決めてもいいですか?
A.主治医から指示された範囲で除水してください。個々の患者さんにより透析後の目標体重、総除水量、時間あたりの許容除水量は異なります。
Q8. 透析スケジュールはどうやって決まりますか?
A.患者さんの日常生活への負担が少なく、かつ十分な透析量が確保できる透析スケジュールを主治医と相談して決めます。
Q9. 深夜透析(寝ながら)はできますか?
A.管理施設の方針と患者さんの体調が許せば、深夜透析を行うこともあります。ただし、全ての患者さんが行えるわけではありません。
Q10. 何か持病や合併症があると在宅透析はできないのでしょうか?
A.持病や合併症の程度によります。持病や合併症により在宅血液透析が行えない場合もあります。
Q11. 施設の外来はどれぐらいの頻度で通えばいいのでしょうか?
A.1か月に1回は必ず通院しなければなりません。また体調など問題があれば、それ以上の頻度での通院が必要になります。
環境に関すること
Q12. HHDに必要な自宅の広さはどれくらいでしょうか?
A.HHDに必要な装置や物品、治療スペースなどを考慮すると全体で9~11m2(畳6畳分)のスペースがあれば、問題なく治療を行うことができます。
Q13. 毎月送られてくる医療用物資はどれくらいの量でしょうか?
A.主な大きな資源として、透析液、ダイアライザ、透析回路などがあります。
また、穿刺張りや消毒キットなどの消耗品を含めると、保管のために約3m2(畳2畳分)のスペースが必要になります。
Q14. 自宅に設置される装置はどれぐらいの大きさですか?
A.業者によってサイズに多少の違いはありますが、一般的には以下のような大きさです。
● 個人用透析監視装置 幅330mm×奥行470mm×高さ1,345mm
● 個人用逆浸透装置 幅330mm×奥行430mm×高さ1,015mm
※ これに加え、軟水器の設置が必要な地域もあります。
Q15. 医療廃棄物の処理に関して教えてください。
A.地域によって処理方法に多少の違いがありますが、一般的には以下のように分類されます。
● 透析回路などの使用済み物品:回路内の排液を行った後、一般ごみとして処理。
● 針や抗凝固剤のバイアル瓶:医療廃棄物として病院で処理
● 透析液の空のボトル:業者による回収
Q16. 自宅の工事はどういう内容が必要なのか教えてください。
A.基本的に、以下の工事が必要になります。
● 給水口の設置
● 排水口の設置
● 電気容量の増強とアース接地工事
Q17. マンション(賃貸住宅)でもできますか?
A.貸主に確認を取り、承諾を得られればマンションでもHHDを行うことは可能です。ただし、必ず給・排水設備の工事内容や水漏れのリスクについて貸主に説明し、了承を得る必要があります。
Q18. 浄化槽設置工事(公共下水設備がない場合)でもできますか?
A.HHDの排水には法的な規則はありませんので、公共下水設備がなくてもHHDを行うことは可能です。ただし、透析排水はBOD(生物化学的酸素要求量)が高いため、公共用水域へ直接放流すると環境への影響が懸念されます。また、浄化槽へ排水すると必要な微生物が死滅する可能性があるため、排水処理装置の設置が望まれます。
費用に関すること
Q19. HHD導入費用はどれくらいかかりますか?
A.機器の設置に伴う工事としては、給排水工事と電気工事が必須となります。最低限で15万~30万円ほど必要です。難しい工事ではありませんが、機器の仕様により接続方法が異なりますので、必ず医療機関への事前確認が必要です。自治体により補助金制度を利用できる場合がありますのでお住まいの地区又は医療機関へお問い合わせください。
Q20. 毎月の患者負担はどれぐらいですか?
A.水道や電気などの光熱費は、月1~2万円ほど現在の費用より上がります。
透析治療に関わる費用は施設での透析と同様、健康保険が適用されます。そのため、医療費については増額することはなく、福祉医療受給証(重度)による「自己負担なし」または特定疾病療養受給証(まる長)により「所得に応じた一定額の自己負担(通常1~2万円/月)となります。更に自立支援医療である更正医療を申請することによって1割負担となり自己負担上限額も変わります。(2500~2万円/月)
例:更正医療(2500円) < 特定疾病療養受給証(1万円) → 自己負担額は2500円
医療費とは別に資材などの配送費用がかかる場合があります。
Q21. 配送費用はどれぐらいかかるのでしょうか?
A.資材の配送費用は、各医療機関により異なりますので、医療機関へお問い合わせください
シャントに関すること
Q22~25
A.準備中
介助者に関すること
Q26. 介助者は何をすればいいのでしょうか?
A.介助者は患者が自分自身でできないことの補助や機器の操作を行います。またトラブルが発生した場合の対処や医療施設に連絡する役割を担います。
Q27. 介助者がいなくてもできますか?
A.在宅血液透析は、医療者がいない状況で血液を一時的に体外に出して行う治療であり、トラブルが起こった場合の危険性を考慮し、トラブル対応ができる訓練を受けた介助者がいることが在宅血液透析を行う条件となっています。
Q28. 介助者の訓練はどれぐらい必要でしょうか?
A.介助者の訓練は患者本人と同じ回数は必要ありません。一般的には数回で済むことがほとんどです。
Q29. 介助者の同意がなくてもできますか?
A.介助者は患者とともに訓練を受ける必要がありますので、同意は必要です。介助者以外の同居家族も協力的であることが望ましいです。
Q30. 介助者は誰でもいいのでしょうか?
A.一般的には介助者は同居家族であることはほとんどですが、同居者がいない場合でも、必ず透析をしている時間に来て頂ける人がいれば、訓練を受けて介助者となることは可能です。
Q31. 介助者を雇う形態は可能ですか?
A.一般の介助者と同様に、透析を実施している時間に必ず来て頂けることと、訓練を施設で受けて頂くことが必要です。穿刺が法的に可能な看護師や臨床工学技士を自費で雇うケースであっても施設での訓練は必要であり、また患者自身の訓練が免除されることはありません。
医療施設に関すること
Q32. 透析施設がHHDを始める時は何から始めればいいですか?
A.HHDを始めるためには施設のシステム作りが必要です。①~⑩それぞれについて医師、看護師、臨床工学技士の役割を明確にし、連携して行います。
① 在宅血液透析施設基準の確認
② 患者・介助者教育
(ⅰ自己穿刺、ⅱ透析実技、ⅲ腎機能・血液透析知識、ⅳ栄養指導、ⅴ生活指導)
③ 緊急連絡方法
④ HHD患者導入手順作成
⑤ 外来受診方法
⑥ 物品輸送方法
⑦ 廃棄物処理方法
⑧ 在宅訪問方法
⑨ HHD機器管理方法
⑩ 機器メーカーとの連携
Q33. 施設がHHDを導入するのに必要な事項を教えてください。
A.施設でHHDを導入するには、在宅血液透析指導管理料の施設基準を満たす必要があります。HHDを実施する施設は専用透析室や人工腎臓装置を備え、患者がHHDを行なっている時間帯に患者から緊急連絡を受けられる体制をとること、また患者の緊急入院に対応できる病床を自施設、あるいは連携施設が確保していること、となっています。
在宅血液透析指導管理料は特掲診療科の届出が必要になります。詳細は令和2年度診療報酬改定、第16の5 在宅血液透析指導管理料をご確認ください。